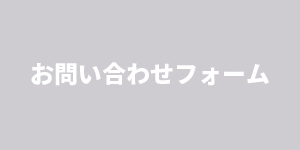花火はなんのために打ち上げられるのか?
今年の長岡花火大会は土日開催で混雑が予想され、本来の戦争犠牲者追悼や平和への願いといった原点が薄まっているというニュースを読みました。そこで、「花火は平和への願いで打ち上げるようになったのは、いつの時代からどのような背景がありますか?」とチャットしてみました。
答えは以下の通り。
花火が「平和への願い」と結びついて打ち上げられるようになった背景には、いくつかの時代的・文化的な転換点があります。以下にその歴史的流れをまとめます。
◆ 江戸時代:慰霊・供養としての花火
◎ 両国川開き(1733年〜)
- 起源は1733年(享保18年)、徳川吉宗が命じた「両国川開き」。
- 前年の享保の大飢饉とコレラ(疫病)によって亡くなった人々の慰霊と供養のために隅田川で花火が打ち上げられたのが始まり。
- このときの花火は、「鎮魂」「悪疫退散」「天下泰平」を祈るもので、政治的・宗教的な意味合いがあった。
✅ この時点で、花火には「死者を悼み、災厄のない世を願う」という意味が込められていた。
◆ 明治以降:娯楽イベント化と戦争との関係
◎ 明治・大正時代
- 花火は庶民の娯楽として発展。
- 供養の要素は徐々に薄れ、祭りや行楽の一部へ。
◎ 戦争と花火(昭和初期)
- 第二次世界大戦中(1940年代)は、多くの花火大会が中止。
- **終戦直後(1945年以降)**には、空襲で焼け野原になった東京などで、再び花火大会が行われ、「平和の象徴」としての意味合いが強まった。
◆ 現代(平成〜令和):明確な「平和祈念」イベントへ
◎ 長岡まつり大花火大会(新潟県)
- 原点は1945年の長岡空襲の犠牲者慰霊。
- 毎年8月1〜3日に開催。「慰霊・復興・平和」をテーマに掲げており、代表的な平和の花火大会とされる。
◎ 各地の「平和祈念」花火
- 広島や沖縄など、戦争の記憶が色濃く残る地域では、8月の「原爆の日」「終戦記念日」前後に平和を祈る意味での花火大会が開かれることもある。
◆ まとめ:いつから「平和の願い」になったのか?
| 時代 | 花火の意味 |
|---|---|
| 江戸時代 | 慰霊・疫病退散・天下泰平(徳川吉宗) |
| 明治〜昭和初期 | 娯楽化、宗教的意味は薄れる |
| 戦後 | 戦争の犠牲者への慰霊、復興・平和の祈りへ |
| 現代 | 「平和の象徴」としての明確な位置づけ |
感想
なるほど、勉強になりました。花火の始まりとなったのは、徳川吉宗の両国川開きなのですね。両国川開きは納涼のための行事で、旧暦5月28日から8月28日までの期間、両国隅田川で夕涼みが許され、川開きの日に花火を打ち上げたそうです。新暦で言うと1733年7月9日が始まりです。徳川吉宗は、目安箱を設置したことでも有名ですが、庶民の声を拾い上げ政策を実行し、飢饉がおきれば庶民のために花火を打ちあげたり、今の日本にこそ必要なリーダーだったのかもしれません。戦後は平和祈念の意味合いが色濃くなり、長岡花火大会はその象徴ということですね。
私は、花火大会は人が混雑するので苦手です。田舎者なので隅田川花火大会も長岡花火大会も行ったことがありません。その代わり、クーラーの効いたリビングを部屋を真っ暗にして、65インチのテレビで、YouTubeの花火大会動画(https://www.youtube.com/watch?v=xcgrIlCBd9w)を観て楽しんでいます。人目を気にせず、特等席で大迫力で楽しめます。最近のテレビは音も良いですね。臨場感もすごいです。
鍵屋と玉屋の違い
花火は「たまや~」とか「かぎや~」と口上することが風習ですが、鍵屋と玉屋の違いについてChatGPTに聞いてみました。
答えは以下の通り。
「玉屋(たまや)」と「鍵屋(かぎや)」は、江戸時代の有名な**花火師の家系(花火屋)**で、今の日本の花火文化の礎を築いた存在です。それぞれに特徴や役割の違いがあります。
| 項目 | 鍵屋(かぎや) | 玉屋(たまや) |
|---|---|---|
| 創業 | 元禄時代(1680年代) | 鍵屋の番頭が独立(1810年頃) |
| 初代 | 六代目鍵屋弥兵衛 | 清七(元・鍵屋の番頭) |
| 特徴 | 花火の元祖、代々続く老舗 | 鍵屋から分家独立した存在、革新的な演出 |
| 口上 | 「かぎや〜!」 | 「たまや〜!」(今もよく叫ばれる) |
◆ 鍵屋とは?
- 江戸幕府から正式に花火の打ち上げを許された、由緒ある花火師。
- 初代は「鍵屋弥兵衛」で、元禄時代から続く。
- 両国川開きで最初に花火を打ち上げたのも鍵屋とされます。
- 当初は仏事・儀式的な意味が強く、格式を重んじた。
◆ 玉屋とは?
- 鍵屋の番頭だった清七がのれん分けされて独立。
- より派手で革新的な演出を取り入れ、江戸庶民に大人気。
- 観客の間では「たまや〜!」の掛け声が流行した。
- しかし火事を起こしてしまい廃業(1843年頃)しており、現在は存在しません。
◆ 「たまや〜!」「かぎや〜!」の意味
- 花火が打ち上がった時に観客が感動や感謝を込めて叫ぶ掛け声。
- どちらの花火かを識別する意味もあった(競演のような構図だったため)。
- 現代では「たまや〜!」の方が有名ですが、現存しているのは鍵屋のみです。
◆ 現在の継承
- **鍵屋は現在も続いており、「株式会社 鍵屋」**としてプロの花火師集団を維持しています。
- 「玉屋」は廃業してしまいましたが、伝説的な存在として名を残しています。
◆ まとめ:玉屋と鍵屋の違い
| 観点 | 鍵屋 | 玉屋 |
|---|---|---|
| 成立時期 | 1680年代(元禄) | 1810年頃(江戸後期) |
| 起源 | 江戸幕府公認の花火師 | 鍵屋の番頭が独立 |
| 特徴 | 伝統・格式 | 派手・革新・人気 |
| 継続性 | 現在も存在(株式会社鍵屋) | 火事により廃業(1843年) |
| 掛け声 | 「かぎや〜!」 | 「たまや〜!」(より有名) |
💡豆知識
現代の花火大会でも「たまや〜!」と叫ぶことがありますが、実際に花火を上げているのは鍵屋だったり、まったく別の会社だったりします。それでも「たまや〜!」が残っているのは、玉屋の華やかな印象が庶民の心に残った証拠です。
感想
なるほど。玉屋が鍵屋から独立したのは創業から100年以上あとですね。社員が革新性を武器に独立するという話は現代でも良くある話です。清七と鍵屋はのれん分けのとき揉めたりしなかったのでしょうか?番頭は現代の会社で言うと部長や執行役員場合によっては副社長的な立場だそうです。調べると八代目の時にのれん分けをしたそうです。
鍵屋が現代でも続いていることも驚きです。もともとの初代は奈良県五條市の出身だそうです。吉野川で葦の管に火薬を練って小さな玉をつくり、「火の花」「花の火」「花火」と称して売り出したところ、飛ぶように売れたことが始まりです。六代目が江戸幕府から両国川開きの花火を任され、十四代目が今の社長で十五代目は次女天野安喜子さんです。安喜子さんは芸術学の博士号(論文タイトル:打ち揚げ花火の「印象」-実験的研究による考察ー)をとり、北京や東京のオリンピックの柔道の審判員もされているスーパーウーマン(ウーマン・オブ・ザ・イヤー2025大賞受賞)のようです。
花火大会の開催が危ぶまれるニュースも見ますが、花火は本当に世界に誇れる日本の伝統技術なので末永く続いてほしいと思います。日本政府は伝統産業にもバラマキして若い人達が伝統を引き継いでいけるようにすべきです。日本の花火師の皆さん、これからも頑張ってください!!!