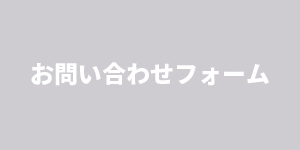今年はさんまが大豊作?
以前、さんまが日本で獲れなくなっているというブログを書きましたが、それに反して今年はサンマが大豊作というニュースをみました。それについてChatGPTに聞いてみました。
答えは以下の通り。
「今年はサンマ(太平洋サンマ)が大豊作では」という話、メディアにもあるけれど、「確実に例年より豊漁」と言い切るのは慎重な部分もある、という情報が多いです。ただ、「豊漁っぽい/例年より良さそう」という見方が出てきている背景には、いくつかの原因が考えられています。以下に、現在出ているデータと仮説を整理します。
出ているデータ・状況
まず、サンマの資源・漁獲について報じられている状況はこんな感じです:
- 気象庁が「黒潮の大蛇行」(黒潮が本来のルートを大きく逸れて流れる現象)が終息したと発表。これがサンマの沿岸来遊にプラスに働く可能性があるとみられている。 テレ朝NEWS
- 港で初水揚げされたサンマの大きさが、昨年より一回り大きい(重量・体長が大きい)という報道が多い。たとえば130〜140gが中心、時に200g近い個体も。 東洋経済オンライン+1
- 水揚げ量そのものは、「昨年並み」の低水準予測という見方が強い。資源量(オフショアの生物量)はわずかに上昇したものの、それでも近年の高水準と比べると低い。NPFC+3Tridge+3アンダーカレントニュース+3
- 初期の水揚げでは、昨年より魚が日本近海(沿岸域)に来ている印象があると報じられている。東洋経済オンライン+1
なぜ「豊漁っぽい」と感じられるか:仮説・要因
上記の状況を踏まえて、「今年が豊漁っぽい」とされる理由として、以下のような要因が挙げられています。
| 仮説/要因 | 内容 |
|---|---|
| 黒潮の大蛇行の終息 | 過去7年9か月続いた黒潮の大蛇行が終わったという発表。これまで大蛇行によって暖かい海流が日本近海を覆い、サンマが本来近づくはずの餌場や通り道が変化し、沿岸に寄りにくくなっていた可能性がある。終息によって、サンマが沿岸域へ来やすくなったとする見方。 テレ朝NEWS+1 |
| 水温・海流の変動 | 春~夏にかけての水温や海の状態がサンマの稚魚の生育に適していた可能性。餌となるプランクトンなどの発生や流れが良かったことが、稚魚の生存率を高めたと見る向き。 note(ノート)+1 |
| 漁獲・漁船活動の変化 | 燃料費の高騰などコストの関係で、ある国・地域の漁船の活動が抑制された可能性があり、それによって日本近海へ来るサンマが「手つかず」のまま到来する割合が増えたのでは、という仮説。 note(ノート) |
| 魚の大きさが増している | 個体が大きく、体重も重めのものが多いということが報じられていて、これが「豊漁に見える」一因。大きい個体は市場で目立つし、漁師・消費者ともに「豊かだ」と感じやすい。 東洋経済オンライン+1 |
注意点・反論・限界
ただし、「本当に豊漁か」「長期的なトレンドの回復かどうか」については以下のような注意点があります:
- 資源量そのものが依然として「低水準」であり、「昨年並み」とされる低いレベルから大幅に改善しているというわけではない。東洋経済オンライン+2アンダーカレントニュース+2
- 沿岸に来る魚の量が多いというだけであって、公海や漁場の全体資源の分布が広く偏っている可能性。つまり「近くで獲れやすい」という局所的な豊かさの感覚が強く出ている可能性。
- 商業的・市場的には「サイズが大きい」ことが良いが、それでも母魚の数や稚魚の生存率の関係で将来どうなるかは予断を許さない。
- 漁獲割当(クオータ)など国際的漁業管理の制度もあり、これがどのように守られるかによって変動がある。The Japan Times+1
総括
したがって、結論としては:
「今年は“例年より望みがある”年。特に沿岸域でまとまったサンマが来ており、魚体も大きめという報告が多く、“豊漁っぽい”感じは確かにある。しかし、漁獲量全体や資源の健全性という点では、まだ昔のような豊かな時代に戻ったとは言えない。持続性を考えると慎重な見方も必要。」
なるほど、水揚げ量自体は昨年並みなのですね。なんかニュースの取り上げ方は錯覚してしまいます。
2025.9.13