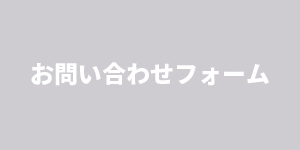画像生成AIは“著作権的に”どこまでOKですか?
画像生成AIは“著作権的に”どこまでOKですか?とChatGPTに聞いてみました。答えは以下の通り。
いい質問です。「画像生成AI(例えばStable Diffusion、Midjourney、DALL·Eなど)」を使ったとき、著作権・知的財産法的にはどこまで許されているかは、現行法・判例・ガイドラインがまだ追いついておらず“グレー領域”が多いのですが、今わかっていることを整理してお伝えします。
以下、主に日本の法制度を前提として説明しますが、国によって規制・考え方は異なるので、その点も注意です。
基本的な枠組み:著作物と著作権の要件
まず前提として、著作権法で保護される「著作物」とは、一般に次のような要件を満たすものです:
- 人の思想または感情を創作的に表現したもの
- 文芸、美術、学術、音楽などの範囲に属するもの
- 他から単純に模倣されたものでない独自性・創作性があること
この前提を踏まえて、AI生成物(画像)をどう扱うかという議論がなされます。
文化庁でも「AIと著作権に関する考え方」などで整理をしています。 文化庁
1. AIが自律的に生成した画像:著作権が発生しないことが多い見解
現状、最も一般的に言われている考え方は:
AIがほぼ完全に自律的に、ユーザーの最小限の指示だけで画像を作るような場合、その画像は“著作物”と認められず、著作権が発生しない可能性が高い。
なぜかというと、「人の創作性・思想・感情の表現」という要件を満たしにくいためです。 文化庁+3NTT+3コーポレート+3
ただし、この見解が絶対的なものではなく、ケースによって異なる可能性もあります。 コーポレート+3Generative AI Media │ 生成AIに特化した専門メディア+3文化庁+3
たとえば、ユーザーが非常に詳細で指示を出し、結果に創作性が認められうるような「人の関与」があると評価されれば、その画像に著作権が認められる可能性もあります。 弁護士法人永岡法律事務所+5コーポレート+5Generative AI Media │ 生成AIに特化した専門メディア+5
また、AI生成物を元に人が後加工をして、創作性を加えるような場合、その改変部分には著作権が認められる可能性があります。 弁護士法人永岡法律事務所+4すすむ・はかどる、契約学習「契約ウォッチ」+4文化庁+4
2. 依拠性・類似性:他者の著作物との関係が重要
もう一方で、生成AIを使う際にもっとも注意すべき論点は、「依拠性(既存の著作物を参考・模倣しているか)」や「類似性(表現が似すぎているか)」です。
- もしAIが生成した画像が、既存の著作物とほとんど同じ構図・デザイン・細部などを含んでいて、「本質的に同じまたは非常に類似」と判断されると、著作権侵害になる可能性が高まります。 北浜法律事務所+5文化庁+5株式会社エルテス+5
- 特に、ユーザーがプロンプトで「この有名画家のこの絵の〇〇風」「特定の作品そのものに近づけて」といった指示をした場合、依拠性が認められる可能性が大きくなります。 株式会社エルテス+3TD SYNNEX株式会社+3文化庁+3
- ただし、画風・雰囲気・タッチなど“スタイル”だけを模倣するのは、アイデア的・技術的なレベルであって表現の保護対象ではないため、必ずしも違法とはなりません(著作権法では「アイデア」は保護対象外)。 文化庁+3株式会社エルテス+3文化庁+3
つまり、完全なオリジナル表現で、誰かの作品と混同されないくらい差異があれば、安全性は高くなります。
3. 学習データ・モデル開発段階の利用と著作権法 30条の4(権利制限規定)
AIモデルを作る際、既存の画像を学習データとして使うことがあります。この点にも著作権法上のルールがあります。
日本の著作権法第30条の4には、「著作物に表現された思想・感情の“享受”を目的としない利用」つまり分析や機械学習などの目的であれば、許諾なしに著作物を一部複製・利用できるという権利制限規定があります。 北浜法律事務所+2文化庁+2
ただし、この利用が「著作権者の利益を不当に害する」ような形をとると例外的に違法となる可能性もあります。 文化庁+4内閣府ホームページ+4企業法務に強い弁護士への相談は大阪「咲くやこの花法律事務所」へ+4
さらに、この「分析目的」での利用であっても、それが直接生成物へ過度に依拠してしまうような場合(依拠性が高い場合)は、著作権侵害と見なされるリスクがある、という考え方が出てきています。 株式会社エルテス+3TD SYNNEX株式会社+3文化庁+3
AIツール(商用サービス、API、アプリケーションなど)を利用する際、多くの場合そのサービスの「利用規約」や「ライセンス契約」があります。その中で次のような規定がされていることが多いです:
4. 利用契約・ライセンス条項の重要性
- 生成物の著作権帰属(ユーザーに帰属するか、サービス提供者に帰属するか)
- 商用利用可否
- 編集・再配布の可否
- 学習データの使用条件
これら規約に違反すると、著作権以外の契約違反として損害賠償を問われることもあります。 弁護士法人永岡法律事務所+2企業法務に強い弁護士への相談は大阪「咲くやこの花法律事務所」へ+2
たとえ法律上問題がなさそうでも、契約違反で使えないケースもあるので、利用するAIサービスの「利用規約」は必ず確認すべきです.
5. 実務的に安全性を高めるポイント
理論上のグレー領域を踏まえて、実際に画像生成AIを使う際にリスクを抑えるための実践的な注意点をいくつか挙げておきます:
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| プロンプトで特定作品を指定しない | 「モネの睡蓮風」など固有作品を指定するのはリスクが高い |
| 出力画像を細かく編集・加工する | 人の創作性を加えることで著作権を主張しやすくなる可能性あり |
| 複数の生成から組み合わせたり差異をつけたりする | 他の既存作品と被らないよう工夫する |
| 利用規約を遵守する | AIサービスの商用利用条件、帰属条項などを守る |
| 権利者に許可を取る | 特定の作品に近づけたい場合などは事前に許可を取った方が安全 |
| 類似性チェックを行う | 出力画像が既存作品に似すぎていないか確認する |
なるほど、他の作品を指定したり規約違反の使い方をしない限り人ではないので著作権は発生しないようですね。