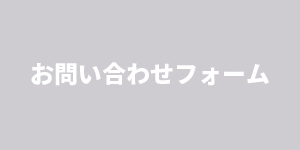午前12時
日本では、日をまたぐ時間は午前0時ですが、WordPressで予約する投稿するときはAM12時と入力します。海外では午前0時ではなく、午前12時なのでしょうか。ChatGPTに確認してみました。
答えは以下の通り。
ご質問の「海外では午前0時ではなく午前12時なのでしょうか」という点について、以下のように整理して説明します。
■ 結論:
午前0時(midnight)は、世界中どこでも「0:00(24時間表記)」または「12:00 AM(12時間表記)」とされており、国によって「午前12時」と呼ぶわけではありません。
■ 詳しい解説:
◉ 24時間表記の場合(多くの国・軍・公共交通機関など):
- 0:00 = 午前0時(midnight)
- 12:00 = 正午(noon)
日本も多くの国もこの表記に準じています。
◉ 12時間表記の場合(アメリカ、カナダ、フィリピンなど):
- 12:00 AM = 午前0時(深夜)
- 12:00 PM = 正午(昼)
→ この点が紛らわしく、日本人が「12時=お昼」と思いがちなのに対して、「午前12時(12:00 AM)」は夜中の0時を指します。
■ つまり:
| 表記方法 | 深夜(午前0時) | 昼(正午) |
|---|---|---|
| 24時間制 | 0:00 | 12:00 |
| 12時間制 | 12:00 AM | 12:00 PM |
■ 混乱のもとになる点:
- 「午前12時」と言うと日本語では非常に混乱します(人によって「夜中」か「正午」か迷う)。
- 英語圏でも “12 AM” や “12 PM” の代わりに、**「midnight」「noon」**と明確に言うことが推奨されています。
■ まとめ:
- 世界的にも「午前0時=0:00」または「12:00 AM」であり、特別に「午前12時」と呼ぶ習慣はありません。
- 「午前12時」という言い方は、日本語独特の曖昧な表現で、できるだけ「0時」または「正午」と明確に言った方が誤解が少ないです。
なるほど、アメリカなど12時間表記の国ではAM12:00を使用するのですね。0時という言い方は24時間制の呼び方らしいです。つづいて、12時間表記の国を挙げてもらいました。
答えは以下の通り。
12時間表記(AM/PM表記)を主に使っている国は、以下のような国々です。
■ 主に 12時間表記(AM/PM) を日常生活で使う国:
| 国名 | 備考 |
|---|---|
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 最も代表的。日常生活・TV・会話でも12時間制が主流。 |
| 🇨🇦 カナダ | 英語圏では12時間制、フランス語圏(ケベックなど)では24時間制も。 |
| 🇦🇺 オーストラリア | 会話や日常生活は12時間制、公共交通や公式文書は24時間制もあり。 |
| 🇳🇿 ニュージーランド | オーストラリアと同様。 |
| 🇵🇭 フィリピン | アメリカ英語の影響が強く、12時間制が一般的。 |
| 🇮🇪 アイルランド | 日常生活では12時間制が使われるが、24時間制も併用。 |
| 🇲🇾 マレーシア | 英語が多く使われる都市部では12時間制が一般的。 |
| 🇮🇳 インド | 書面や公式は24時間制もあるが、会話では12時間制が主流。 |
| 🇵🇰 パキスタン | 英語表記・日常生活で12時間制が多い。 |
| 🇧🇩 バングラデシュ | 同上。英語の影響で12時間制が一般的。 |
| 🇳🇬 ナイジェリア | 英語圏のため、12時間制が多い。 |
| 🇯🇲 ジャマイカ | 英語圏。日常的に12時間制。 |
■ 備考:
- 多くの国では 公的機関・軍・航空・鉄道などでは24時間制 を使用する傾向があります(例:アメリカの軍隊や病院)。
- 一方で、日常会話・テレビ・カレンダー・学校の時間割などでは12時間制が主に使われています。
- 欧州諸国(例:フランス、ドイツ、スペインなど)は日常でも24時間制が一般的です。
■ 結論:
アメリカを中心とする英語圏の多くの国では、日常生活では12時間制(AM/PM)を主に使用しています。ただし、公式な表記や技術的な用途では24時間制と併用されることもあります。
なるほど、アメリカでも軍や病院では24時間制なのですね。日本ではどうでしょうか?次に、ChatGPTに「日本の12時間制と24時間制の歴史について教えてください。」と聞いてみました。
答えは以下の通り。
【1】江戸時代まで:伝統的な「不定時法」
◉ 概要
- 日本では明治時代以前、**「不定時法(ふていじほう)」**という独自の時間制度が使われていました。
- 一日を昼と夜に分け、それぞれ6等分。つまり昼の長さ・夜の長さに応じて「一刻」の長さが変わる方式でした。
- 「九つ」「八つ」「七つ」などの呼び名で時刻を数えていました(例:午前6時頃=「明け六つ」、午後6時頃=「暮れ六つ」)。
【2】明治時代(1873年):24時間制への移行
◉ 太陽暦(グレゴリオ暦)と定時法の導入
- **1873年(明治6年)**に、日本は太陽暦(グレゴリオ暦)を導入。
- 同時に**「定時法」=1日24時間制**が正式採用され、不定時法は廃止。
- 西洋式の「午前(AM)・午後(PM)」の概念もこの時代に導入されました。
【3】戦前・戦中(昭和初期まで):12時間制の普及
- 明治〜昭和初期にかけては、**12時間制(午前○時/午後○時)**が主に日常生活で使われるようになりました。
- 政府・軍・国鉄などの公式機関では次第に24時間制も使われるようになりますが、庶民の間では12時間制が主流でした。
【4】戦後(1945年〜):24時間制の拡大
◉ 公共機関・マスメディアの影響
- 戦後の復興とともに、鉄道やバスの時刻表、放送時間の表記などで24時間制が一般化。
- 特に国鉄(現・JR)の時刻表やテレビ番組表などで24時間制が広く普及しました。
【5】現代(1990年代〜現在)
◉ 実態:両者併存
- ビジネスや公共交通、医療、軍事、IT関連などは24時間制が基本。
- 一方で、日常会話・テレビ番組・学校の時間割・アナログ時計などでは12時間制(午前/午後)が今も根強い。
【まとめ】
| 時代 | 主な時間制度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 江戸時代以前 | 不定時法(昼夜6分割) | 季節によって時刻の長さが変わる |
| 明治時代 | 24時間制(定時法) | 西洋式の導入。12時間制も併用開始 |
| 昭和前期 | 主に12時間制 | 午前・午後が主流 |
| 戦後 | 24時間制が急速に普及 | 公共機関やメディアが推進 |
| 現代 | 両者併用 | 目的や文脈により使い分け |
なるほど、日本でも12時間制が使われるのに午前12時と呼ばないのは何故でしょうか?最後に、ChatGPTに「なぜ日本だけ午前0時と呼ぶのですか?」とチャットしてみました。
日本で「午前0時」と呼ぶのは、日本語の表現文化と、12時間制の論理とのズレによるものです。これは日本独自の呼び方というより、「午前12時」と言うと混乱を避けるためにあえて“午前0時”と呼ぶようになったという経緯があります。
■ 結論:
日本では「午前0時」と表現するのは、12時間制の「午前12時」が非常に紛らわしいから。明確な区別のために“0時”という24時間制の表現が日常語として定着したのです。
■ 背景と理由
1. 12時間制には「午前12時」≒「深夜0時」という混乱がある
| 表現 | 実際の時刻 | 誤解のリスク |
|---|---|---|
| 午前12時 | 0:00(深夜) | 昼と勘違いされやすい |
| 午後12時 | 12:00(正午) | 午後なのに12時という語感に違和感 |
→ 英語でも「12:00 AM = midnight」「12:00 PM = noon」という混乱があるため、明確に midnight(深夜) や noon(正午) と言い換えることが推奨されます。
2. 日本語では「午前・午後12時」の表現が曖昧に聞こえる
- 「午前12時」と聞いたときに、「え?夜中?昼?」と感じる人が多い。
- 特に高齢者や一般生活者にとって、「12時=昼」という思い込みがあるため、混乱を防ぐために“午前0時”と呼ぶのが一般的になった。
3. 24時間制が日常に浸透している日本社会
- 鉄道の時刻表、テレビ番組表、病院の予約システムなど、多くが24時間制を採用。
- そのため「0:00」が「午前0時」として自然に浸透。
4. 言語文化の違い
- 英語:混乱しやすくても「12:00 AM」「12:00 PM」で表現する文化。
- 日本語:曖昧さを嫌い、「0時」「24時」「正午」など明確に分ける文化が強い。
■ まとめ
| 表現 | 日本(一般的) | 英語圏(一般的) |
|---|---|---|
| 深夜 | 午前0時(0:00) | 12:00 AM |
| 正午 | 正午(12:00) | 12:00 PM |
| 午前12時 | 使われにくい(混乱防止) | 12:00 AM(混乱あり) |
| 午後12時 | ほぼ使わない | 12:00 PM(正午) |
■ 補足:なぜ「午前0時」でなく「午前12時」にならなかったか?
数学的には「午前12時」が0時を意味すると言えなくもないですが、「12時=昼」という感覚が日本語には根強いため、それを避ける形で「午前0時」が定着したと考えられます。
なるほど、午前12時というと昼と勘違いされるので、24時間制の0時を使うようになったのですね。スッキリしました!
午後12時は、普通「お昼の12時」って言ったりしますね。他にも丑三つ時とか知りたいので、日本の不定時法については、また今度このブログで取り上げようと思います。